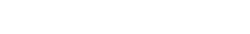第30話 メロンつる割病(ツル〔蔓〕ワレ・ビョウ)
メロンの美味しい季節です。北海道産のメロンは贈答品として大人気です。その栽培で最も重要な病害の一つがメロンつる割病。連作地で発生が多く、露地栽培、ハウス栽培ともに発生しています。
《 アサガオ、キュウリ、メロンなどのツル〔蔓〕とは 》
アサガオやキュウリを育てるのに支柱を立てます。これに「ツル」が巻き付いて、植物が生長してゆきます。このような植物(=つる性植物)では、茎の部分も含めツル〔蔓〕と呼称します。何やらややこしい話ですが、今回の病名と関係がありますので記憶しておいてください(写真①、②)。本シリーズ第21話(メロンつる枯病)も参照していただけると嬉しいです。
|
▲①アサガオの蔓 |
▲②キュウリの蔓 |
《 病徴 》
初期病徴としての葉枯症状
この病気は、病原菌が根から植物体内に感染して、茎や葉の養分・水分通路に侵入します。通路は維管束(いかんそく)といい、動物の血管に相当します。外から見たこの病気の初期症状は葉に現れ、一見すると葉の病害と誤診される恐れがあります。早朝は、株全体に生気がなく水の上がりの悪い株がみられます。始めのうちは、日中は回復しますが、次第に葉が葉脈に沿って褐変枯死します(写真③)。
|
▲③葉枯症状 |
進行病徴としての萎凋症状
病勢が進展すると、ついには株全体が著しい萎凋症状を示すようになります。中心部にある太い根の先端部はあめ色に変わり、根や地際部の茎を横に切るとその断面では維管束が褐変しています(写真④)。
次に収穫穫間近の萎凋症状を写真⑤、⑥に示しました。果実を実らせようとメロンが一番頑張っている時に、体内に潜伏していた病原菌が一挙に活動し、養分や水分を奪ってゆくためです。過去には、このような症状がハウス全面に及ぶ事例もありました。
|
▲④初期・萎凋症状 |
|
▲⑤成熟期・萎凋症状1 |
|
▲⑥成熟期・萎凋症状2 |
末期症状としてのつる割れ症状
さらに症状が悪化すると、地際部の茎(メロンではこの部分を「親づる」と呼んでいますが)に亀裂ができ、「ヤニ」を生じます。この末期症状の茎の亀裂を指して、つる割病という病名が付いたのでした。しかし、実際の畑でこの症状を見かけることはごく稀です。茎は割れずに、その表面に黒褐色の「ヤニ」(始めは赤色です!)を生じます。この病斑はさらに拡大してかさぶた状となり、多湿条件が続くと地面に近い部分に、分生子(病原菌の胞子)の塊がつくられます。この鮭肉色(=サーモンピンク)の塊には、スポロドキア(=胞子塊:ほうしかい)という名前が付いています。
《 伝染経路と発生環境 》
病気にかかったメロンは枯れてしまいます。これを罹病残渣(リビョウ・ザンサ)といいます。つる割病の第一の伝染源です。残渣の中には、分厚い壁に包まれた病原菌の胞子(=厚壁胞子:コウヘキホウシ)が潜んでいて、メロンの根の先端(根毛)から侵入するのです。もう一つの伝染源は、種子です。病気に罹ったメロン種の中に、病原菌が潜り込んでいるのです。厚膜胞子は生存力が強く、長年にわたり土中でじっと潜んでいます。つまりメロンの連作は、発病を助長します。高温・乾燥年には発病が目立ちます。
《 防除法 》
1.施設栽培では、太陽熱や薬剤による土壌消毒を行います。
2.健全種子を用い、種子消毒を行います。
3.無病苗を定植し、病株は見つけ次第除去します。
4.この病気に対して、抵抗性品種が開発されています。しかし抵抗性品種に打ち勝つように変異した病原菌グループ(=レース)も出現していますので、慎重な品種選択が必要です。
《 病原菌と寄主範囲 》
この病原菌は、メロンにしか感染しません。病原菌が感染・発病させることのできる植物のグループを寄主範囲といいますが、この菌は寄主範囲が一つということです。名前はFusarium oxysporumf.sp. melonis(フザリウム・オキシスポーラム・フォルマ・スペシャーリス・メロニス)。全世界共通の呼び名です。